【 この記事は約 14 分で読めます】
最近ニュースやSNSで「減税やります!」という話題が出ると、必ずと言っていいほど聞こえてくる声があります。
「レジの税率変えればすぐできるじゃん」
…いやいや、現場を知っている人間からすると、それは超甘い考えなんですよ。
私は某百貨店で、情シスと売場の両方を経験してきましたが、
過去の増税対応では、まさに本当に地獄を見ました。
だからこそ、ただ反論したいわけじゃなくて、
「税率変更で小売の裏側では何が起きるか?」を少しでも知ってもらいたいたくて、この記事を書きました。
——ということで、今回はその「減税が簡単じゃない理由」と「小売の裏側」を少しだけお話させてください。
レジだけじゃないんだよ問題
「レジの設定を変えるだけなら簡単でしょ?」
確かに、レジの設定を変える”だけ”なら簡単だと思います。
それこそ設定画面で「8%→0%」と数字を変えて、棚札を貼り替えれば終わり…というのは表面的には正しいです。
でも、それは”レジ”と”値札”という、あくまでお客様の目に見える部分の話なんです。
過去の増税対応も色々な準備を何ヶ月という時間をかけて裏側でしっかりやっているから——
すぐ出来たように見えているだけです。
税率が変わると、何が起きるのか?
税率が変わると、影響を受けるのはレジだけではありません。
具体的には、こんなところに波及します。
・商品や原材料の仕入価格にも税率が絡む
・仕入帳簿(商品カテゴリごとに税率記録が必要)
・在庫管理システム、ERP、会計システムなど、すべて税率と連動している
・店頭の運用変更
そして、一部上記と被りますが、増税でも減税でも避けられない作業がこちら
・値札の全面貼り替え
・POP・広告・カタログ紙面の修正
・ECサイトの価格表示変更
・システム減税変更
・帳票や伝票の見直し
・社内マニュアルや教育の更新(レジ操作・税率変更前後の返品どうする?など)
ということで、バックエンドの運用だったり、システム改修は必須なんです。
これらの存在を知っていたら簡単に出来るとか絶対に言えるはずもないです。
なので良い機会なので、ぜひ知ってください!
税率変更=システム改修=お金がかかる
プログラマーなどからは「システム改修?必要ないよ。定数いじれば終わりでしょ?」とかいう声もあるんです。
確かに税率のような数字は「定数」としてプログラムの中にまとめておけば、
変更も簡単に済むはず——というのが理屈です。
POSレジなどは、多くは機械とソフトがセットになったパッケージ型のシステムなので、
税率っていうのがパラメータで変更できるようになっていることが多く、変更も比較的スムーズです。
でも、バックエンドの業務システムではそうはいきません。
税率が変わると請求書、領収書、売上計算、会計連携、CSV出力、API連携など、あらゆる機能に影響します。
これらは定数化されていなかったり、税率が直接プログラムに書き込まれていたりすることもあるので、
日本全体を見たら、システム改修が必要な企業はとても多い。と考えて間違いありません。
中小企業では、システム化されておらずExcelでそれらを管理してたりするケースもあり、
一筋縄で行かない場面もチラホラ出てくると思います。
ほら…Excelって作り手によって綺麗、汚いがはっきりわかるじゃない?
セル毎に直接、「本体価格×税率」とか値入ってたらどう?漏れなく直すの大変じゃない?
——とか、作ったのが昔すぎて仕様忘れちゃった!とか、さらに作者が退職してたら本当最悪ですよね。
製造業や卸売業も関係あるよ
っと、ここまでは販売店の視点で話をしていましたが、
製造業や卸売業も「販売店に商品を売る」ので、当然そこでも消費税の処理が必要になります。
では、卸が販売店に売るときに、POSレジ使うと思いますか?
…レジ使わないんです。
POSレジは、店舗での対面販売やレジ打ちに使うもので、「販売店と消費者」の間で使われます。
一方、卸売業のようなBtoB(企業間取引)では、
見積書、請求書、納品書、仕入伝票などの帳票を、紙やPDF、あるいはEDI(電子データ交換)でやり取りしています。
その中で消費税率がどう計算されるか、どのタイミングで適用されるか、帳票にどう表示されるか——
すべてが業務システム側のロジックに依存するんですね。
つまりPOSレジのように「税率をパラメータで変えればOK」というわけにはいかず、
税率変更が帳票出力や会計連携にどう影響するかを、システム全体で確認する必要があるんです。
定数を変えれば良い…わけがない
そして、定数を変えただけで済むのは、”表面上”だけの話
実際には「本当に全部ちゃんと動くか?」を確認するためのテストが必要になります。
特に、独自システムを作り込んでる企業では、税率ひとつ変えるだけでも数十万~数百万の費用が発生します。
税率の値を「8%→0%」にする設定変更”だけ”であっても、
その変更が他のシステムや帳票などにどう影響するかを確認するために全体の動作テストが必要です。
膨大なお金がかかるのも、設定変更費用というより、ほとんどがテスト費用みたいなもんです。
なぜなら、バグや不具合って本当に予想外のところでおきますし、コスト削減でテストを抜くとかは考えられません。
・「小数点の桁が多すぎて処理落ち」
・「特定の文字列が含まれていたからエラー」
・「ある日付が原因でシステム停止」
…こんな”嘘だろ?”って思うような不具合だって本当にあるんです。
販売価格や卸への支払いで何かあったら信用失墜も間違いないので、
システムに手を加える場合、ただの値変更であってもテストは絶対に必要なんです。
そして、上記のような理不尽な不具合対応で、
システムベンダーから何百万ものプログラム改修費用を請求されることも現実には、”ある”んです。
そして、その納得できない請求を理詰めで抗議して減額させるのも情シスの仕事だったりします。
(システムベンダーって平気で自分の会社の不手際をユーザー責任って押し付けてくるかんね…)
過去の増税対応で何が起きた?
——っと、話がそれましたが、過去の税率変更は直近だとこんな感じかな?
・2014年:消費税5% → 8%
・2019年:消費税8% → 10% + 軽減税率導入
この時、現場ではこんな対応をしていました。
・POSレジの設定変更
・会計システムの税率変更
・軽減税率対応「食品8%、食品でも酒は10%、他10%」の判定ロジック追加
・値札の全面貼り替え(店頭だけでも数十万点規模でした…)
・紙伝票の印字ロット廃棄&再印刷
余談:インボイス制度の衝撃(2023年)
「インボイスは税率と関係ないよ?」なんてことはないです。
むしろ、税率と密接に関係しているのがインボイス制度の本質です。
SEとして税務や会計システムに関わっている立場から言わせてもらうと、本当にゴミみたいな制度でした。
いや、制度の理念は理解できます。消費税の透明性を高めて、仕入税額控除の適正化を図るという目的は立派です。
でも現場への負担があまりにも大きすぎました。
仕入れ先とのEDI(電子取引)や請求書フォーマット、会計帳票の全面見直しとか、
しかも、これ1社だけじゃなくて、取引先すべてに影響するので、調整が地獄。
一応、EDIなんかは業界で統一されたフォーマットはあるんですが、電子データを紙の伝票に紐付けする必要があったりすると、
各社ごとに仕様が違うので、取引先ごとに対応がレイアウト変更が必要だったりするので、
問屋が数社に絞られていない限り、統一化なんて夢のまた夢なんです。
百貨店って地域物産を仕入れたりする関係で、個人商店規模との取引も多いからね。
あとは、商品ごとに適用税率を明示することが義務付けられたので、
請求書や帳票類に「この商品は10%」「この商品は軽減税率8%」といった、税率区分を明確に記載しなければいけなくなりました。
商品分類ロジックの実装が必須で、これがまたシステム的にめちゃくちゃ面倒でした…。
値札とタグの付け替え
食品や小物は、ほとんどがバーコードで管理されているので、
値札の貼替えはそこまで多くありません。
棚札を付け替えるぐらいで比較的スムーズでした。
…とはいえ、数十万点ある商品の棚札を一斉に変えるのは、やっぱりキツかったです。
値札じゃなくて棚札ね。表示価格の方。
そして、問題はバーコードがない商品たち。
・地域物産とかマイナーな製造所の商品
・銘酒の類
・衣類 → タグを流通過程で付け替えるため、貼り替えが複雑
こういう商品らは、単に「値札貼り替えりゃいいじゃん」って言葉では済まないんです。
単純に想像してみてください。
お店にあるすべての棚札や値札を漏れなく、一斉に、人力で貼り替える作業。
電子棚札?あんなの結局電波だから足元とか角地は電波悪くて更新されねーよ!!(怒
これがどれだけ大変か。
より専門的な店の品揃えはバーコードがほとんどないから、
店内を見渡す限りの商品、倉庫在庫も含めて、全部貼り替える必要があるんですよ。
令和の現在はどう?
とはいえ、過去の増税対応でシステム改修を経験した企業は、
「多分また税率変わるだろうな…」という前提で設計しているはずなので、
今税率が変わっても、当時ほどの混乱にならないかもしれません。
ただし、新しく出来た企業や、税率変動を想定していないシステムを使っているところは、
今から地獄を見る可能性があります。
税率変更は、過去に経験していても油断できないし、
初めて対応する企業にとっては、想像以上に大掛かりな作業になります。
あと”商品を売る”立場としては、表示価格に偽りが絶対にあってはならないので、
すっごい神経使います。
1円で表示とレジで違うとブチ切れて数時間怒ってくるクレーマーとかもいるからね。
表示より高いなら素直にごめんなさいだけど、安く売ってても関係ないからね。
なぜこんなに大変なの?
理由はシンプル。
日本の小売業はシステムが複雑すぎるからです。
表に見えるのは「レジ」だけ。
でも実際には、税率変更はいくつものシステムに影響します。
・POS(販売管理)
・在庫管理
・会計
・仕入れEDI(電子取引)
・ECサイト
これらがすべて税率と密接に結びついています。
さらに中小企業では紙文化が未だ根強く残っていて、
「伝票に印字された税率をどうする?」っていう超アナログな問題も発生します。
ざっくり言ったらこんな変更が必要。
・FAX注文書、納品書などの様式の変更
・印刷された伝票の場合は印刷ロットで何千~何万単位の新発注
・古い伝票は廃棄 → コスト&時間がかかる。
そんな弱小アナログ企業に対応する体力ある?
「自然淘汰だよ、ついて来れないなら切り捨てりゃええやん…」って残酷な意見もあります。
でもね、売上規模が小さくても、企業従業員が少なくても、素晴らしいもの作っている企業はいっぱいあるんですよ。
そんな企業を見捨てるなんてとんでもない…。むしろ保護すべき存在ですらあると思います。
卸・製造業側にも影響あるよ
税率変更は小売だけじゃなくて、サプライチェーン全体に波及します。
卸売業
・請求書フォーマット変更
・在庫評価の再計算(税率込で管理している場合)
製造業
・原材料仕入れの税率変更 → 原価計算の見直し
・長期契約の価格調整 → 契約書再締結の可能性
EDI取引
・電子データの税率部分の更新→システム改修必須
・※無税の場合、システム的には「0」「空白」を区別する必要がある場合もあり
・更に非課税、不課税の判定条件などを考慮が必要
つまり、税率変更は「レジの設定」どころか、
「取引の根本ルール」そのものに手を入れなきゃいけないんです。
短期間でやれと言われたら…
もし政府が突然、「来月から減税ね!」
…なんて言ったらどうなると思いますか?
とりあえずシステム的な観点でざっくりいうと、
まず、対応期限が限られることからシステム会社への依頼が殺到します。
そして、システム会社のリソース不足になり、納期遅延、コスト爆増ってことになって、
SEもプログラマも受入する小売側も関係者全員ゾンビになります。
しかも、システム改修は基本的に「信頼のおける普段付き合いのある会社」に依頼します。
導入ベンダーとかね。
何も知らない会社に仕様書をポンっと渡しても、すぐに対応できるわけがないんですよ。
だから、「世の中にいくらでもシステム会社あるから対応できるでしょ!」
…なんて話にはならないんです。
あとベンダーの担当って、関東圏、関西圏、とかエリアごとに請け負っていることが多いんです。
だから仮に依頼できたとしても、
「うちの会社だけ最優先で!」なんて無理な話。
だってシステム改修を担当する人は有限で何社も掛け持ちしてるんですもの。
ちなみに過去の増税やインボイスのときは、法案成立から対応までに2年ぐらい?猶予期間があったと思うのですが、
期限ギリギリのところでは、有名どころのシステム会社ですらパンクしていました…。
それが現実です。
税率変更を”短期間でやれ”と言われることが、どれだけ小売やシステム会社を虐めることなのか。
ちょっとは知ってほしいよね。
0%より1%の方がまだマシかも?
これは情シス担当として、超重要な視点なんですが…
「消費税 0%より1%の方がまだマシ説」
…あると思うんです。いや、ほんとに。
なぜか?
帳票の非表示処理が不要
0%だと「消費税欄の値を消す」か「非表示」にする必要が出てくる場合があります。
システム屋としては、「0%なら0」って表示したいんだけど、
「0%なら空欄にしろ」とか言う頭悪い偉い人、絶対出てくるんですよ。
そうなると、「0=空欄」っていう謎ロジックを入れなきゃいけないので、
帳票レイアウト改修は結構地獄だったりします。
私なら全力で「0は0だ、空欄は諦めろ!」って言うけどね。
既存システムの税率テーブルを活かせる
1%なら単純に税率の値を変更するだけ。
0%だと「非課税扱い」になり、ロジック分岐が増える。
つまり1%なら既存の仕組みを活かせるんですね。
インボイス対応との整合性
0%だと「課税取引」じゃなくなるケースがあり、
仕訳や請求書の処理が複雑化する恐れがあります。
税込表示義務の混乱回避
税率を1%にしておくと「税額」が発生するため、税抜き・税込みの区別が明確に保てます。
税率が変わっても計算ロジック自体はそのまま使えるので、
システムや帳票運用にも支障が出にくいんです。
一方で、税率が0%になると、実質的に税抜きしか存在しなくなってしまい、
「これは課税体操か?非課税なのか?」といった税区分の判断が曖昧になります。
将来的に税率が復活した場合には、再度ロジックの組み直しやシステム改修が必要になり、
現場が混乱する可能性も高まります。
現場の人って、販売やレジ操作など入力はプロフェッショナルですが、
会計や税務の専門家ではありません。
なので、区分ごとの処理や時系列に応じた計算など、少し複雑な判断が求められると、
どうしても戸惑ってしまうことがあって、それは決して悪いことではなく、
人それぞれ得意分野が違うだけ——って話なんですが、
だからこそ、そういった部分はシステム側でしっかり補ってあげる必要があって、
そのシステムは絶対に間違いがあってはならないよう作らないといけないの。
言い方に語弊あったらゴメンね。私はどっちも判ってる人だから他意はないよ。
ってことで、0%より1%の方が、
現場負担は圧倒的に軽い…ような気がします。
海外との比較:なぜ日本はこうなる?
欧米では、税率変更があっても比較的シンプルに対応できます。
なぜなら「外税表示」が基本だから。 値札に「+tax」と表記されてるケース多いですよね。
つまり、レジの設定を変えれば済むケースが多く、
値札やPOPをいちいち貼り替える必要はありません。
でも日本は違います。
何故なら「税込み表示が義務化されている」ため、
システム以外にも値札・広告・ECまで全部修正しなければいけない。
これが日本特有の”大変なポイント”なんです。
まとめ:現場を知らないと見えない現実
というわけで——
「レジで設定変えるだけだから減税は簡単!」っていうのは、本当に表面だけを見た話です。
政府が「レジシステムの運用変更に時間がかかる」という説明をするのは、
単純に一般人に説明しやすいよう「レジ」という言葉を使っているだけで、
その裏には、膨大なシステムと物流の運用が控えているのご理解いただきたいです。
実際に必要な対応は——、
・レジ設定
・仕入れ処理
・帳簿会計システム
・値札・広告、EC表示
・現場運用変更
・システム会社のリソース確保
…など、すべてが日本全国で対応しなければいけない、超・大掛かりな物流対応になります。
「政府の対応が遅い!早くしろ!」って言うのは別にいいけどさー(いいのか?)
それは同時に、現場に強い圧力をかけていることも忘れないでほしいです。
制度変更のたびに、現場の方々——
特に経理や情報システム部門など、表に出ない”裏方”の人たちが、膨大な作業と調整に追われています。
白鳥が水面上で優雅に泳いでいても、水面下では必死に足を動かしているように、
現場は静かに、でも確実に戦っているんです。
私は現在、小売業界から他業種に移りましたが、(あまりにもつらくて)
今でも現場で奮闘している皆さんを心から尊敬しているし応援しているよ!
このブログが、少しでも「現場の現実」を知ってもらうきっかけになれば嬉しいです。
長々とお読みくださり、ありがとうございました!
 ちこ
ちこ税率変更はレジの設定だけじゃない。
現場はもっと大変だよー!
すべての後方部門に幸あれ!
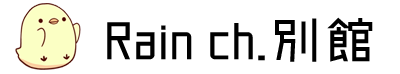
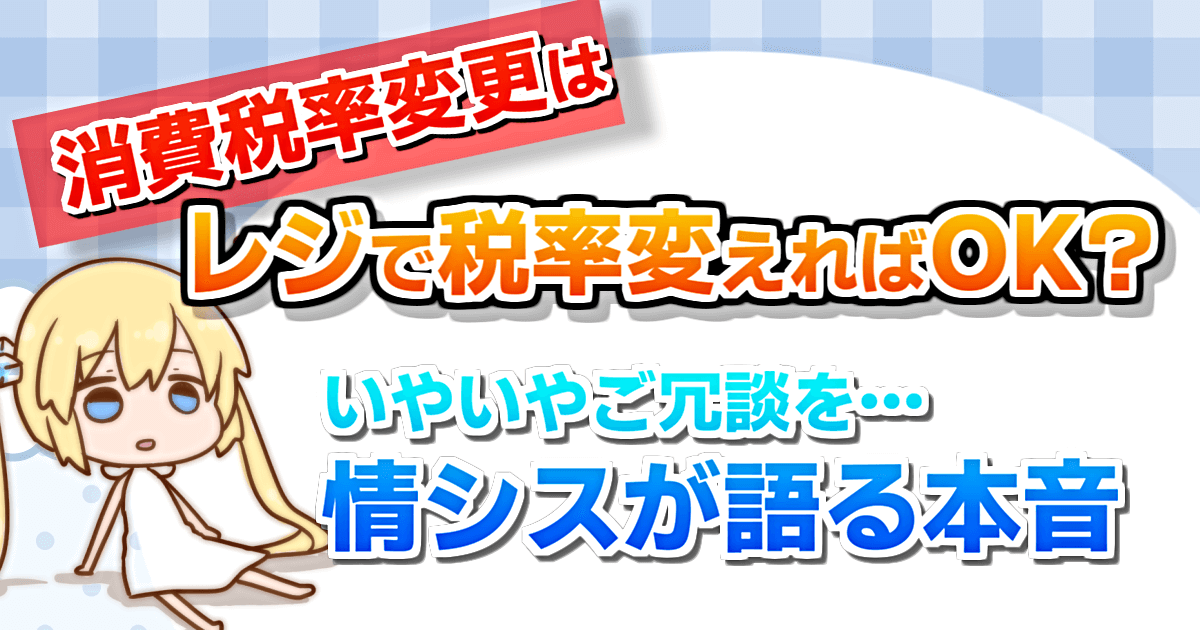
コメントはお気軽に!